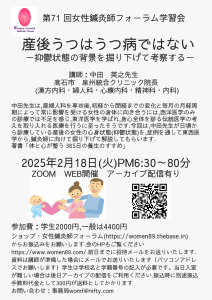こんにちは、中田先生のお話を聴講された方、質問をされた方へ、回答が届いておりますので、参考にしてください。
①なかなか患者さんとの関係が深まらないと見抜けない部分であって難しいし、対話や慶弔が必要なのでしょうが、治療家として、まず、何から手をつければよいとお考えですか?アドバイスをお願いします。
回答:
患者さんそれぞれで対応が違うので、「何から手をつければよいか?」に答えるのはなかなか難しいですね。対話を通してエピソードを確認し、分析と構造化が必要です。その際、あらゆる症状には必ずそこに至るまでのエピソードがあるということです。その症状を取り除くという考え方で向き合うと全体像を診ることはできません。症状を善し悪しで考えるのではなく、その症状が出る必要があった、その人にとって必要な事が起きているという見方で観察をしながら、会話を進めていくのが重要ですね。そして患者さんが口から出す言葉にも、その言葉が出る必然性、理由があります。なぜ、その言葉を使う必要があったのか?そういう聞き方が大事です。そして、その上で、傾聴を通して共感すること。共感することで相手は受け入れられていると感じます。そのように向き合えば、自ずと今、何が必要かが見えてくると思います。
そして、関係性が深まってしまうと、バイアスがかかってしまいます。先入観をもって診てしまうようになるので、むしろ、初診で関係性が深まっていないときにいかに、しっかりと観察するかがその後に大きく影響しますね。当院でも、研修生の予診では出てこなかったことが、本診察では、本人が自ら話すことも多々あります。それは、こちらが的確に状況を把握して、必要な質問を投げかけるからです。「観察」の次に「観察」。とにかく観察ですね。挙動や声の変化、姿勢、視線、全てが大事なメッセンジャーです。
②養生の話で麦茶は陰性で×ということですか?ホットでもダメでしょうか?いままで水分補給に向いていると進めていました。白湯も冷め得たらダメですよね。
回答:
麦茶は冷薬です。温かくして飲んでも、体を冷ます生薬ですから、冷やしてしまいますよね。私は患者さんにそのように説明をしています。また、白湯とは、温かい湯のことを言いますので、冷たいものを白湯とは言いませんよね。しばらく放置していて冷めてしまった時、夏と冬でも温度は違います。ぬるいぐらいならよいですけど、冷たいものはもはや白湯ではありません。白湯の定義は、沸騰して少し冷めて飲める温度になったお湯、です。
③先生は漢方を出す際に、所見は東洋医学、西洋医学どちらもトルのでしょうか?
回答:YES。どちらか一方ではダメです。
④東洋医学で腹診が出てきましたが、やはり脈診、舌診等も併せて証を立て、漢方を出されているのでしょうか>
回答:脈診します、舌診もいたします。ただ、それらの所見はその瞬間瞬間の移りゆく変化を示していますから、変化の方向性を見極める為の情報収集活動と理解しています。処方は道具の一つですし、手技もまた道具の一つです。全ての所見は「結果として」目の前に呈示されていますので、「証」はある意味、結果の表現型ですよね。それ故、その証になるエピソードを理解し、患者さんと共有をしてからそれぞれの役割を明確にし、処方は道具の一つとしてどう利用するのかを一緒に考える。そのように考えています。
講師の中田英之先生に感謝申し上げます